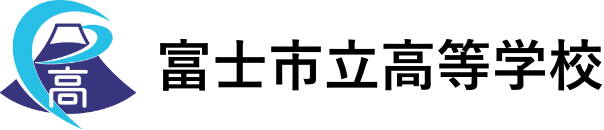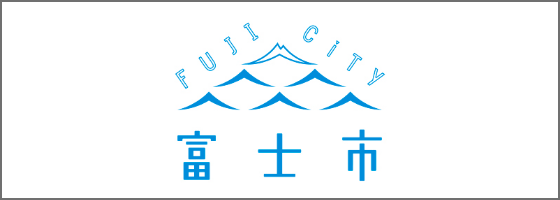社会を動かす挑戦者たち(3年総合探究科)
今回の集中研修では
“社会課題に取り組む市民になる”
をコンセプトに学びを深めました。
テーマは以下の4つです
・社会全体で「がん」に向き合う
・多文化共生を考える
・子育てとキャリアの両立
・共生社会を見直す
これまで、市役所プランを通して富士市の課題には向き合ってきました。
今回はさらに範囲を広げての挑戦です。
事前学習では基本的な用語の理解や、どんなステークホルダーがいるのかを想定していきました。
昨今の課題の多くは関係性の中で生じるものです。その実態を想定していきました。
また、2日の午後には富士市役所と富士市立病院より、それぞれのテーマで講演をしていただきました。
富士市の現状を把握することで、より課題が身近に感じられる機会となりましたね。
”富士市だから”、”富士市でも”という問題があったかと思います。
9月3日のスタディツアーでは都内で活動している団体へ訪問し、当事者や支える人たちの声を聴いたり、現状を実感してきました。当事者の肩越しから見える世界を経験する時間となりました。
最終日は、リディラバ様よりワークショップでの課題整理です。これまでの経験を通して、問題の構造を理解し、解決策を考えていきました。
課題の提示の際には、根拠を示すことで納得性を高める工夫が随所に見られました。解決方法も既存の機会を用いるなど、現実に即した内容が提示されました。
これまでの学びが蓄積できていますね。
ハーバード・ケネディ・スクールのロナルド・ハイフェッツは問題について「技術的問題」と「適応課題」を定義しました。技術的問題は既存の方法で解決できるもの、適応課題は当事者の認識や関係性を変えなければ解決しない問題です。今回、皆さんが考えた問題はどちらだったでしょうか。これから皆さんが出会う課題はどちらの課題でしょうか。
これからも共に、「自律する若者」へと成長していきましょう!